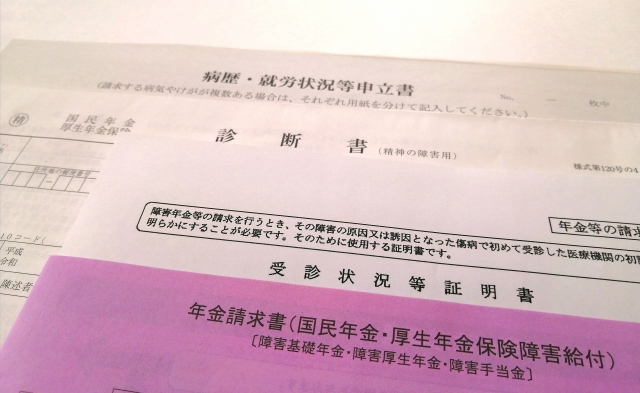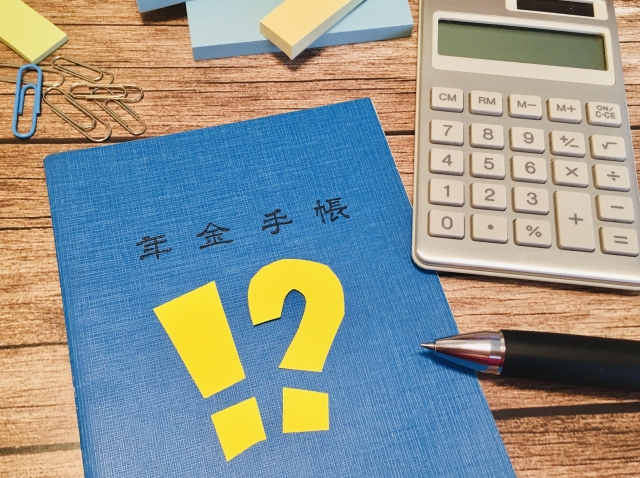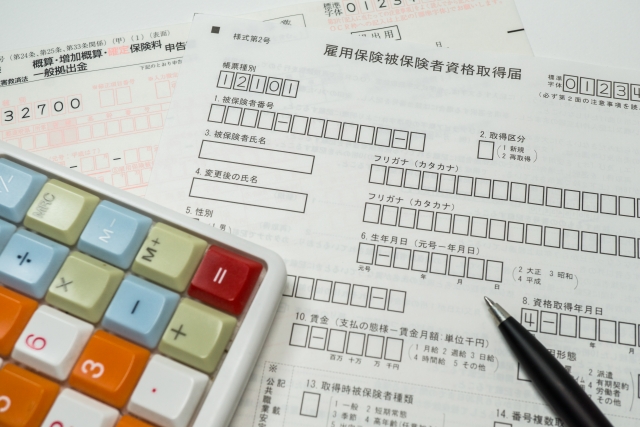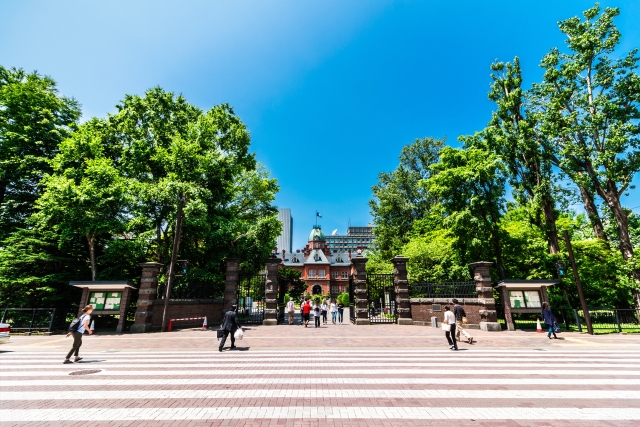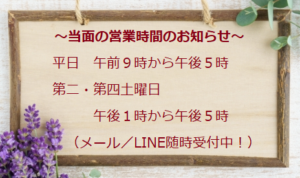みなさん、ご無沙汰してました💦年度末年度初めの手続きや報告業務が盛りだくさんで、しばらくホームページに手を付けられていませんでした。お役立ちミニ講座も3か月ぶりですが、今日はいつかはしっかりお伝えできたらいいなと思っていた「変形労働時間制」について、解説できればと思います。
みんな、ぼくのこと忘れてないよね。中小企業事業主お助けわんこのしろ吉です!労働時間は1日8時間、1週40時間までっていうのは僕も知っているけど、変形労働時間制ってことはこれとは違う取り扱いがあるっていうことなのかな。
しろ吉くんの活躍の場をしばらく奪ってしまってごめんね。そうなのよ、週休二日制の企業だったらこれにあてはまるんだけど、少数精鋭の中小企業では必ずしもそのルールにあてはめると、なかなかうまくいかない場合もあるのよね。
ぼくの会社は中小の建設業だけど現場の人なんかは、4週6休が基本だから、この1か月の変形労働時間制を取り入れているんだ。ぼくも詳しくは分からないんだけど、これにすると適法に時間外労働を少し抑えられることができるんだって、総務の人が言ってたよ。
さすが、かえるちゃん、何でも知ってるわね。変形労働時間制は3種類くらいあるんだけど、今日はこのうち「1か月単位の変形労働時間制」について、詳しく解説していくから、しっかりついてきね!
1か月単位の変形労働時間制の基本的仕組みを理解しよう!
【基本】1か月単位の変形労働時間制とは
1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場※は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。
※常時使用する労働者が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業
なるほど、平均して40時間になれば、1日8時間を超える日や、1週間で40時間を超える週があってもOKってことだね。だからかえるくんの建設業の会社だったら、1週間で6日の週もあるから、これが1日7時間としても1週間で軽く40時間を超えちゃうけど、この変形労働時間制だったら、平均して40時間であれば、適法にシフトが組めるってことかなあ。
さすがしろ吉くんは理解が早いわね。そうなのよ、4週6休の会社だと、よほど1日の時間が短くない限りは、週6日働くとその週は週40時間は軽く超えてしまうわよね。これで1か月単位の変形労働時間制を採用していないと、所定労働時間で週40時間超えるからこれは違法ってことになってしまうの。定休日が少ない飲食店で毎月シフトを組んで回しているところや1か月の範囲内で毎月の20日以降が忙しいとか予め決まっているような事業だったら、その週だけ所定労働時間を長めに設定できたりします。
ってことは、忙しい週は1日10時間とか、1週48時間に設定しも、平均して1日8時間、1週間40時間以内なら、1日10時間で設定した日で8時間超えたところや、1週48時間で設定した週で週40時間を超えた時間でも法定時間外労働にはならないってことですね!
そう、そのとおり💝これで今日の講義は半分理解できたわね(^^;)
そうしましたら、具体的にこの変形労働時間制を導入するにはどういった手続きが必要なのか見て行きましょう。
1か月単位の変形労働時間制を導入するために必要なこと
1か月単位の変形労働時間制を導入するには、
労使協定または就業規則等で、以下の事項の全てを定める必要があります。
なお、常時使用する労働者が10人以上の事業場は就業規則の作成・届出は必須となります。10人未満の事業場でも就業規則に準ずる規程が必要です。また、
労使協定を締結して定める場合は、労働者の人数に関わらず、所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。
①対象労働者の範囲
対象労働者の範囲については制限はありません。同じ事業場でも適用になる人とならない人を定めても大丈夫です。
②対象期間および起算日
対象期間および起算日は具体的に定める必要があります。なお、
対象期間は1か月以内の期間に限ります。
例:毎月1日を起算日とし、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする←給与計算の起算日に合わせるのがベスト。
③労働日および労働日ごとの労働時間
シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業所は44時間)を超えないように設定しなければなりません。具体的な勤務日、勤務時間は事前にカレンダーなどで通知するにしても、就業規則や労使協定書には対象期間中の1週平均の労働時間、各日の始業・終業時刻(パターンがある場合は全て)、休憩時間、休日等を定めておく必要があります。
④労使協定の有効期間
1か月単位の変形労働時間制を適切に運用するためには、1年~3年以内程度に設定するのが望ましいです。
⇒労使協定を締結する場合は、必ず届出が必要になりますが、有効期間をいつまでにしているか確認が必要で、期間更新の度に届出が必要になります。
(ただし、労働者10人未満の事業所で就業規則のみで定める場合は特に届出の必要はない。)
【参考】
1か月単位の変形労働時間制 協定書記載例(福井労働局HP)
シフトとかは予め決めておく必要があるとのことですが、いつまでという決まりはありますか?
遅くとも起算日の前日までには特定する必要がありますが、労働者も直前まで予定が分からないと、困るので、いつまでに知らせますということを規定などに定めておいた方がよいですね。
平均して週40時間の計算って、結構大変かもと思うのですが、注意することはありますか?
そうね、実務的にはここからが一番大事なことで、月の暦日数によって上限時間があるから、そこを超えないようにという確認が必要なのと、あとはどの時間が割増賃金の支払いが必要ないわゆる「法定時間外労働」になるのか、導入する際にはしっかり理解しておかないといけないです。
労働時間の計算方法
対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は週44時間)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。
✅上限時間の計算方法
上限時間 = 1週間の労働時間40時間(特例措置対象事業場44時間)× (対象期間の暦日数/7)
通常は対象期間を1か月とするので、その場合の上限時間は以下のとおりになります。
【対象期間が1か月の場合の上限時間】(単位:時間)
週の法定
労働時間 |
月の暦日数 |
| 28日 |
29日 |
30日 |
31日 |
| 40 |
160.0 |
165.7 |
171.4 |
177.1 |
| 44 |
176.0 |
182.2 |
188.5 |
194.8 |
1か月単位で見ると暦日数によって、上限時間が異なることが分かりますね。また例えば月何日を休みにするとかによって、1日の所定労働時間の上限も自ずと決まって来るので、導入するときにはしっかり考えて導入しましょう。厚生労働省のモデル就業規則にも、細かくその規定例や時間の定め方などが掲載されていますのでぜひ参考にしてくださいね。
割増賃金の支払(1か月単位の変形労働時間制での「法定時間外労働」はどの時間になるのか?)
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な「法定時間外労働」となる時間は以下の通りです。
✅①1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日(※)は8時間を超えて労働した時間
※なお、ここで所定労働時間を例えば1日7時間20分とした日について、7時間20分から8時間までの働いた時間は「所定時間外労働」となり、その部分は通常の時間単価の賃金(割増は不要)の支払いが必要になります。
✅②1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間 (ただし、①で法定時間外労働となる時間を除く。)
✅③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(ただし、①または②で法定時間外労働となる時間を除く。)
なるほど~、もともとどのようなスケジュールで決められているかで時間外になるかならないかが変わってくるということですね。1か月のうちとても忙しいところが決まっていたら、そこの所定労働時間を予め長く設定して、暇なときは短くしておけば、繁忙時期に1日8時間超えても所定労働時間を超えなければ法定時間外労働にはならないということですよね。
そう、そのとおり。ポイントとしては、まず1か月の総枠の時間を確認⇒その枠の中で、1日の所定労働時間を日ごとに設定していくという流れになります。それを超えなければどのようにシフトを組んでも大丈夫です。法定時間外労働の数え方は、まずは一番小さい単位(日)から数えて行って、次(週)、次に(月)全体でみていくようになります。大きい単位ではみ出た時間のうち、既に小さい単位で時間外労働になっている時間はもちろん省いて大丈夫です。以下、1か月単位の変形労働時間制のリーフレットに、法定時間外労働の考え方や例が掲載されていますので、参考にしてくださいね!
1か月単位の変形労働時間制をうまく活用するためにどうしたらよいか。何よりもきちんと管理ができるかが大事。
1か月単位の変形労働時間制が、中小企業にとっては有効的というのは分かったけど、事業主さんにおススメするのに、予定の組み方とか時間外労働の集計とかが結構ハードル高いんじゃないかなあと思って。どうやって提案すればよいのでしょうか?
そうねえ、確かに「言うは易く行うは難し」ということかもしれないけど、まず規程に定めたあとの問題としては以下の2点に集約されると思うのよね。オフィスこころでも新規設立の夜勤ありの建設業の事業所さんが最近これを導入して自動の給与計算の設定まで持っていけたところがあるので良かったら参考にしてみてください!
問題①予定をどのように立てるか?
予定については、とりあえず1か月単位のシフトを事前に組むことが大前提なので、予定を組む際に、所定労働時間が月単位で1か月の総枠を超えないように気をつけることが第一です。1日の所定労働時間が一定のところは事前に1日何時間(パターンがあればパターンを設定)、月の休日が何日というのを決めておくと労働者にもわかりやすいし、カレンダーも作成しやすいと思います。静岡労働局のホームページで各月の休日日数と所定労働時間を定める労働時間チェックカレンダーがありましたので、有効に活用してみるのもよいかもです。
【参考】変形労働時間チェックカレンダー(静岡労働局HP)
オフィスこころにはこれより細かく各日各月ごとに労働時間や休日を設定できるカレンダーツールがありますのでご相談いただいた事業所様はお試しできます(^^ゞ
問題②時間外(所定時間外、法定時間外)労働時間をどのように効率的に正確に集計するか?
あまり時間外労働が発生しなさそうなところは、それほど大変ではないかもしれないですが、時間外労働がよく発生しそうなところは、自力で集計しようとすると3段階で見る必要があり、正直大変かもしれません。時間外労働時間が給与計算結果にも響いてくるので、間違ってはいけないところになります。エクセルの関数なども利用して、正確な集計が行える方法を考えましょう。
①②とも効率よく解決できる方法として、勤怠管理システムの導入を推奨します!
この二つの問題を一度に解決できる方法として、オフィスこころではking of timeという勤怠管理システムの導入を提案しました。一人月額330円で「シフトパターンの作成から毎月のシフト組み~労働者の勤怠打刻~時間外労働などの集計~給与計算」までをシステム管理でき、従業員もスマホなどで打刻してスケジュールや労働時間の確認ができるものになります。オフィスこころも、もしタイムカードのみを渡されて、この1か月単位の変形労働時間制の給与計算をお願いしますと言われたら、自力で集計するのはお断りするかもです(;'∀')勤怠管理システムですと、予め1か月単位の変形労働時間制の設定をしおくと、打刻した時間に対し、対象期間単位で何時間が時間外労働にあたるか?が自動的に集計されるので、日々の勤怠時間の確認をしておけばあとは機械にお任せということが究極にはできるのです。もちろん、機械計算+目視確認でより間違いのない給与計算を行うのがベストであります。人間が一から集計を行う人件費よりもはるかに安くつくと思いますので、導入を検討される事業所様は勤怠管理システムの導入とセットで行うことをお勧めします。
ぼくの事業所は1か月単位の変形労働時間制を導入しているけど、給与計算はどうしているのかなあ。まだタイムカード使っているし、総務の人が月初に忙しそうなのはこの集計をしているのかも。人数が少ないからまだやっていってるのかなあ。今度勤怠管理システムをお勧めしておくよ。
オフィスこころの所見
久しぶりのお役立ちミニ講座でしたが、変形労働時間制の第一弾として1か月単位の変形労働時間制を紹介しました。実はこの変形労働時間制で結構大手企業でも労働者から訴訟を起こされていることがあって、時間外労働は削減できるかもしれないけど、なかなか管理が難しいというのがネックとなっているみたいです。管理がうまくできないくらいなら、正直導入しないほうがよいのではと思うくらいです💦
ぼくも今日色々お話を聞いて、時間外労働で悩める中小企業の事業主さんのお役に立ちたいと思ったけど、なかなか導入までのハードルは高いのかなと思いました。でも、勤怠管理システムがうまく導入できれば、その道筋も見えてきそうです。
そうなのよね、今まで猶予されていた建設業や運輸業、医師の労働時間の上限規制がこの4月から始まりましたが、労働時間の管理はますます重要視される時代になってきて、お困りの事業主さんも多いと感じます。変形労働時間制を導入してもしなくても、労働時間を適切に管理し、労使双方に見える化を図ることが、お互いの信頼関係を構築するためにも重要です。そうすれば訴えられることもありませんからね。見えないから不安になるのです。そのためのひとつのツールとして勤怠管理システムは、有効的な手段かと思います。オフィスこころで紹介したもの以外にも業種によって適切なシステムもあるかと思いますので、色々検討してみるのも良いですね。オフィスこころでは、「勤怠管理システムの設定が難しい、正しく運用できるか不安だ」という事業主様向けに設定支援(遠隔対応実績あり)なども行っております。またその事前段階としての相談や就業規則などの改定についても対応可能です。できる限りになりますが、もしご希望があればお早めにお問い合わせくださいね。
※オフィスこころはking of time公認の導入支援パートナーです。またking of timeのOEM製品であるオフィスステーション勤怠、freee勤怠管理Plusなどにも対応可能で、その他のシステムと合わせて提案可能です。